舞楽 春鶯囀一具
ぶがく しゅんのうでんいちぐ
GAGAKU:Japanese traditional court music
Bugaku;Shunnōden Ichigu
(Bugaku;Gagaku suite:The Nightingale Sings in Spring)
クレジット
収録情報
昭和48年4月16、17日 世田谷公会堂
収録曲
|
舞楽 春鶯囀一具
ぶがく しゅんのうでんいちぐ Bugaku;Shunnōden Ichigu(Bugaku;Gagaku suite:The Nightingale Sings in Spring) | |||
|
1 |
壹越調調子(02'11") いちこつちょうちょうし Ichikotsuchō Chōshi(Modal Prelude for Ichikotsu-chō) |
||
|
2 |
遊聲(05'35") ゆうせい Yūsei(Processional) |
||
|
3 |
序(13'54") じょ Jo(Prelude) |
||
|
4 |
颯踏(08'11") さっとう Sattō(Stamping) |
||
|
5 |
入破(05'25") じゅは Juha(Entering and Broaching) |
||
|
6 |
鳥聲、急聲(10'29") てっしょう、きっしょう Tesshō/Kisshō(Bard Tune/Quick Tune) |
||
time:0.54 s・

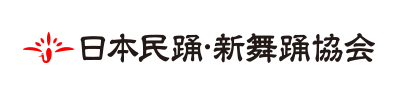
作品紹介
全員が宮内庁の楽師からなる雅楽紫絃会の名演、「舞楽 春鶯囀一具」全曲初録音(1973年)が待望の初CD化。
〈演奏者〉
鞨鼓:安倍季巌
太鼓:東儀信太郎
鉦鼓:大窪永夫
笙:豊雄秋、林広一、多忠麿、豊英秋
篳篥:東儀博、東儀良夫、東儀兼彦、安倍季昌
龍笛:上近正、山田清彦、芝祐靖、上明彦
オリジナルLP盤は、『雅楽(舞楽) 春鶯囀(一具)』(SJL-57)として1973年(昭和48年)7月25日 ビクター音楽産業株式会社から発売。
監修:安倍季巌(日本藝術院会員・前宮内庁楽部楽長)
解説:木戸敏郎
録音:1973年(昭和48年)4月16、17日 世田谷公会堂
題字:前田青邨(日本藝術院会員)
オリジナル・ジャケット・デザイン仕様
「春鶯囀一具」は舞楽の中で大曲として特別に尊重されている名品。中国唐代に皇帝が鶯の鳴き声を曲に写させたものと言われ、さながら鶯の囀りが変奏されていくかの如き典雅な趣をもつ。『源氏物語』には光源氏がこの曲を舞う場面も登場する。全曲揃った一具としては長く演奏されず幻の大曲と称されたが、昭和42年(1967年)3月国立劇場第二回雅楽公演「舞楽」にて、宮内庁式部職楽部楽長・安倍季巌氏の5年間に及ぶ整理・研究と指導によって、遂に「春鶯囀一具(舞楽)」の復活演奏が実現。本盤はその6年後に再び安倍氏の指導の下、宮内庁の演奏家で構成された「紫絃会」が録音した記念碑的アルバム。舞楽用の大太鼓の迫力ある音、管方の響きも良く、力強い見事な舞楽吹[舞立(まいだち)]の演奏となっている。
〈ライナーノーツ〉(10ページ)
作品について
「春鶯囀一具」木戸敏郎
GAGAKU(English brief note)※英文解説
演奏者紹介
使用楽器図版
紫絃会(しげんかい) Shigenkai
本アルバムは紫絃会名義だが、通常は雅楽紫絃会と称した。紫絃会は全員が宮内庁式部職楽部の演奏家で構成され、第17回芸術祭レコード部門芸術祭賞を受賞した『雅楽大系』(昭和37年[1962年]、6LP、日本ビクター、後に当財団から初CD化)、『神楽』(昭和41年[1966年]、6LP、日本グラモフォン)などのレコード録音のほか、放送、舞台演奏等で活動。昭和52年(1977年)2月から翌53年2月までの三回の国立劇場雅楽公演を、宮内庁楽部に代わって雅楽紫絃会が担当し、昭和52年10月、カールハインツ・シュトックハウゼン作曲、雅楽の楽器と四人の舞人のための『ヤーレスラウフ(歴年)-リヒト(ひかり)より』(Der Jahreslauf - Licht)のオリジナル・ヴァージョンを世界初演。
昭和53年(1978年)に国立劇場が雅楽と聲明の共演による舞楽法会を企画したのを契機に、雅楽紫絃会は宮内庁以外の民間の雅楽演奏団体も加わるかたちで東京楽所(とうきょうがくそ)へと発展的に解消した。
なお雅楽紫絃会の大きな業績である『雅楽大系』の当財団からのCD復刻版(VZCG-8125~28)の解説書には、雅楽紫絃会の詳細な活動史にも触れた芝祐靖氏執筆の「雅楽紫絃会顛末記」が掲載されているので、ぜひご参照下さい。