唯是震一 協奏曲を弾く
ゆいぜ・しんいち きょうそうきょく・を・ひく
Shin-ichi Yuize plays his Concertos
ゆいぜ・しんいち
Koto and Sangen:Shin-ichi Yuize Shakuhachi:Hozan Yamamoto Condctor:Michiaki Okuda, Kotaro Sato Orchestra:Nihon Philharmony Chamber Orchestra Tokyo Symphony Orchestra
収録情報
1:1961年9月7日都市センターホールにて録音 2〜11:1986年2月27日ゆうぽうと簡易保険ホールにてライブ録音
収録曲
|
1 |
箏とオーケストラのための協奏曲風六段(08'24") こと・と・おーけすとら・の・ための・きょうそうきょくふうろくだん Concertante ‘Rokudan’ for koto and orchestra |
||
|---|---|---|---|
| 原曲:八橋検校 / 編曲:唯是震一 箏:唯是震一 指揮:奥田道昭 日本フィルハーモニー室内楽団 | |||
|
尺八、箏とオーケストラのための協奏曲第三番
しゃくはち、こと・と・おーけすとら・の・ための・きょうそうきょくだいさんばん Concerto No.3 for shakuhachi, koto and orchestra | |||
| 作曲:唯是震一 箏:唯是震一 尺八:山本邦山 指揮:佐藤功太郎 東京交響楽団 | |||
|
2 |
Ⅰ Allegro ma non troppo(05'45")
|
||
|
3 |
Ⅱ Adagio, alla Okinawa(05'20")
|
||
|
4 |
Ⅲ Rondo, Allegro(03'50")
|
||
|
三弦、尺八とオーケストラのための協奏曲第五番
さんげん、しゃくはち・と・おーけすとら・の・ための・きょうそうきょくだいごばん Concerto No.5 for sangen, shakuhachi and orchestra | |||
| 作曲:唯是震一 / オーケストレーション:デーヴィド・ローブ 三弦:唯是震一 尺八:山本邦山 指揮:佐藤功太郎 東京交響楽団 | |||
|
5 |
Ⅰ Allegro ma non troppo(05'45")
|
||
|
6 |
Ⅱ Adagio elegiaco(03'02")
|
||
|
7 |
Ⅲ Rondo, Allegro(05'27")
|
||
|
箏とオーケストラのための協奏曲第十四番
こと・と・おーけすとら・の・ための・きょうそうきょくだいじゅうよんばん Concerto No.14 for koto and orchestra | |||
| 作曲:唯是震一 / オーケストレーション:デーヴィド・ローブ 箏:唯是震一 指揮:佐藤功太郎 東京交響楽団 | |||
|
8 |
Ⅰ Allegro moderato(05'40")
|
||
|
9 |
Ⅱ Andante(05'20")
|
||
|
10 |
Ⅲ Allegro-Adagio-Allegro(08'11")
|
||
|
11 |
箏・打楽器とオーケストラのためのカプリチオ(08'30") こと・だがっき・と・おーけすとら・の・ための・かぷりちお Capriccio for koto, percussion and orchestra |
||
| 作曲:唯是震一 箏:唯是震一 指揮:佐藤功太郎 東京交響楽団 | |||
time:0.54 s・

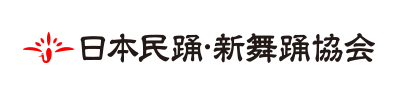
作品紹介
現代邦楽界の第一人者、唯是震一畢生の名演!
自選のコンチェルトを演奏した感動のステージをデジタル録音した1986年の名盤をCD復刻。
CD化に際し、師ヘンリー・カウエルの下での修行時代に大指揮者ストコフスキーから勧められて書いた「箏とオーケストラのための協奏曲風六段」を追加収録!
「唯是作品を特色づけるのは、日本的情緒を損なわずに、しかも純粋で明解な論理的作曲である」(上野晃)
唯是震一は邦楽界にあって西洋クラシック音楽の作曲法を修め、十二音技法をはじめモダニズムを通過した存在として、その作品は戦後注目を集めました。200曲をゆうに越える多作の作曲家ですが、主要作品のほとんどはCBS・ソニーの『唯是震一の音楽』(全10巻LP盤21枚)に収録(現在は廃盤)。
大正12年(1923年)に北海道の箏曲一家に生まれた唯是震一は幼い頃から箏に親しみ、中学時代に作曲家・早坂文雄と出会い楽理を学びます。やがて東京音楽学校邦楽科(生田流箏曲専攻)、次いで東京芸術大学楽理科に転じて昭和28年(1953年)に第一期生として卒業。翌年から米国コロンビア大学で現代アメリカ作曲界を代表するヘンリー・カウエルに師事。日本伝統音楽のなかで育った唯是震一は、カウエルの下で、生来のスケールの大きな音楽性を揺るぎない構造で具体化する技術を身につけ、以後、十二音技法を用いた作品や日本やアジアの伝統的旋法を素材とした作品を次々と作曲します。作風としては、現代的作法と伝統的な方向との折衷主義はとらず、作品ごとに音素材を統一的手法で追究する点が特徴といえます。今回のCDに収録された作品は、十二音技法など現代音楽的なものは含まない、いずれも日本の伝統的な5音階に基づく作品です。
『協奏曲風六段――箏とオーケストラのための』はアメリカ留学中でオーケストレーションを学んでいた頃の作品。日本の伝統的箏曲を素材に、箏とオーケストラの協奏の初期の試みといえます。一部で雅楽の楽器の音色を模しています。
『協奏曲第三番――尺八、箏とオーケストラのための』は、1959年に山本邦山の初リサイタルのために作曲された作品。尺八と箏のカデンツァが聴きどころです。
『協奏曲第五番――三弦、尺八とオーケストラのための』は、元は独奏三弦と邦楽器群のために書かれ、1964年に唯是震一自身の第5回作品発表会で常磐津文字兵衛の三味線独奏で初演されました。後に、門弟の米国の作曲家デーヴィド・ローブがオーケストレーションを行い、現在のかたちとなりました。
『協奏曲第十四番――箏とオーケストラのための』は、1976年にピアノと箏のかたちで最初の二楽章を作曲、ここに1952年の邦楽コンクール優勝作『箏とオーケストラのための小協奏曲』を第3楽章に加え、デーヴィド・ローブが全体のオーケストレーションを行って1977年に完成しました。
『箏・打楽器とオーケストラのためのカプリチオ』は、コロンビア大学留学中の1954年に作曲し、アメリカ作曲家協会主催の作品公募に出品して入選した作品です。
〈ライナーノーツ〉
米寿を迎えて/唯是震一
唯是震一 人と芸術/岸辺成雄
作品紹介/唯是震一(「協奏曲風六段」)、上野晃
演奏者プロフィール
唯是震一(ゆいぜ しんいち) 〈作曲・箏・三弦〉プロフィール
1923年北海道に生まれ、3歳より箏を始める。中学時代に早坂文雄に師事。小樽高商(現小樽商大)を経て東京音楽学校邦楽科さらに芸大楽理科に入学、宮城道雄に師事。1950・1951年に邦楽コンクール作曲部門第2位。1952年に同コンクール第1位、文部大臣奨励賞、日本放送協会技能賞、東京新聞社賞、日本三曲協会賞を受賞。1953年アメリカに留学、コロンビア大学にてヘンリー・カウエルに師事。1954年アメリカ作曲家協会主催の作品公募に「箏、打楽器とオーケストラのためのカプリチオ」を出品し入選、NBC交響楽団と協演。以後ニューヨーク・フィル、サンフランシスコ響等と度々協演。1955年クック社から自作品及び古典の演奏をレコーディングして全米で発売され、ベストセラーとして表彰される。以後アメリカ、フランス、日本の多くのレコード会社から演奏及び作品がレコード化される。
1970年からは毎年リサイタルを開いており、全国各地でのリサイタルや公演、N響・日本フィル・大フィル・京響等オーケストラとの協演、作品演奏会を毎年行うなど、作曲家として又演奏家として広く活躍。海外でもヨーロッパ、アメリカ、中近東、アジアの各地で公演。これまでにニューヨーク・フィル、サンフランシスコ響等と共演、カーネギー・ホール、リンカーンセンターをはじめとした世界の主要ホールに出演。また1958年パリのユネスコ本部落成記念行事及び国際音楽評議会主催の会議とユネスコ世界音楽祭に参加、テヘラン国際音楽祭など、国際音楽祭にも多く招かれている。
作曲活動では1959年以降、毎秋作品発表会を催しているほか、「なよたけ」「楊貴妃」「夕鶴」、映画「天守物語」の音楽を担当。
遠野市名誉市民。1988年紫綬褒章、1995年勲四等旭日小受章を受章。2007年日本芸術院賞を受賞。財団法人正派邦楽会理事、現代邦楽作曲家連盟会長、元NHK邦楽技能者育成会講師。