完売致しました
日本音楽の巨匠 現代箏曲 ── 沢井忠夫
にほんおんがく・の・きょしょう げんだいそうきょく ── さわい・ただお
Masters of Japan KOTO CONTEMPORARY/SAWAI TADAO
収録曲
|
1 |
詩曲1番(14'39") しきょくいちばん POEMEⅠ pour shakuhachi et koto |
||
|---|---|---|---|
| 松村禎三作曲 箏:沢井忠夫 尺八:横山勝也 | |||
|
2 |
箏二重奏曲「波」(10'12") ことにじゅうそうきょく「なみ」 NAMI for koto duo |
||
| 杵屋正邦作曲 箏:沢井忠夫、沢井一恵 | |||
|
3 |
二面の箏と十七弦のための「三つのエスキス」(09'33") にめん・の・こと・と・じゅうしちげん・の・ための「みっつ・の・えすきす」 TROI ESQUISSE pour 2 koto et 17string koto |
||
| 清水脩作曲 第一箏:沢井忠夫 第二箏:井原潤子 十七弦:沢井一恵 | |||
|
4 |
旅懐(インプロヴィゼイション)(10'21") りょかい(いんぷろゔぃぜいしょん) RYOKAI improvisation |
||
| 山本邦山作曲 箏、十七弦:沢井忠夫 尺八、インド笛:山本邦山 | |||
|
5 |
火垂る〜Ⅱ〜箏独奏の為に(11'10") ほたる〜2〜ことどくそう・の・ために HOTAERU-Ⅱ for solo koto |
||
| 沢井忠夫作曲 箏:沢井忠夫 | |||
time:0.38 s・

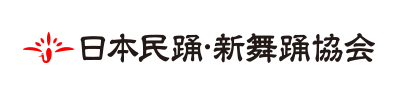
作品紹介
日本音楽の巨匠 Masters of Japan
日本の伝統音楽の粋を集めた「日本音楽の巨匠 Masters of Japan」はレコード・メーカー4社(キングレコード、コロムビアミュージックエンタテインメント、財団法人ビクター伝統文化振興財団、日本クラウン)の合同企画です。
美しい日本語がもっているメロディと響き、和楽器の音色とサウンドが醸しだす情感こそが“和”の味わいです。この「日本音楽の巨匠 Masters of Japan」シリーズのすべてのアルバムが、日本の伝承音楽文化の真髄を伝えています。日本に生まれ育った人なら、自然と身の内に染み込んでいるものばかりです。「日本音楽の巨匠」たちの演奏との出会いは、あなたの内なる日本文化=和との出会いとなり、あなたの中のある日本の再発見となるでしょう。
日本を代表する伝統音楽文化の担い手であり、“人間国宝”をはじめとする誰もが認める超一級の演奏者たちの“至芸”との出会いをお楽しみください。まず、最初に本物の“芸”を体感していただきたいのです。
50代の若さでこの世を去った沢井忠夫。その演奏に接したことのある全ての人々が、叶わないと知りながらも、是非もう一度聞きたいと願うであろう、不世出の天才箏曲演奏家でした。東京芸術大学卒業後、ほぼ同じ世代の山本邦山、青木鈴慕等と切磋琢磨しながら独自の演奏技法、作曲法を自らのものとし、その天性ともいえる研ぎ澄まされた感覚から紡ぎ出す音楽は、沢山のファンを獲得しました。出演したネスカフェTV-CM「違いの判る男」は、箏曲界のスターとしての沢井忠夫を全国に強く印象付けました。
また、その演奏の素晴らしさに魅せられた作曲家から多くの優れた作品を提供されました。
このアルバムには、その中から選び抜いた名曲を収録しました。
解説:田中隆文「沢井忠夫の果たした役割」
曲目解説:藤本草、長尾一雄、清水脩、沢井忠夫
この作品は、VZCG-726として再発売されています。
こちらのページをご覧ください。
沢井忠夫(さわい ただお)プロフィール
(生田流箏曲家、作曲家)1937年 愛知県生まれ。
尺八家であった父の影響を受け、10歳の頃より箏を学ぶ。
1960年 東京芸術大学邦楽科卒業。
1962年 同大学専攻科卒業。在学中、NHK「全国今年のホープ」に選ばれる。
1964年 民族音楽の会(青木鈴慕、沢井忠夫、伊藤松博、高野和之、杵屋栄三郎、山本邦山)を結成。東京芸大卒業後より開催を続けたリサイタルにおいて「箏」という楽器に新しい世界を広げ、現代邦楽の第一人者の地位を築いた。また古典からジャズ、クラシックまで幅広いジャンルを箏で表現する様々な試みを通じて、箏音楽の領域拡大に多大な貢献を果たした。
1971年 「沢井忠夫箏独奏会」の成果に対し芸術祭優秀賞受賞。以後1977年、1983年に重ねて受賞。
1981年 芸術祭レコード部門において「沢井忠夫箏の軌跡」が優秀賞を受賞。
1984年 第2回中島健蔵音楽賞受賞。
活動の場は日本のみならず、アジア、欧米各国に及び、その演奏は常に絶賛を博した。また、創作活動も旺盛に行い、「情景三章」「讃歌」「鳥のように」「甦る五つの歌」などの箏独奏曲、「上弦の曲」「風の歌」などの箏・尺八二重奏曲から、箏、三弦の大合奏曲まで、現在もなお演奏家達がこぞって取り上げる優れた作品を多数発表した。さらに、演奏活動の傍ら後進の指導育成にも精力的に取組み、自身が主宰する沢井箏曲院を創設した。
1997年 4月1日死去。