ノイズレスSPアーカイヴズ 伝説の歌声 3 イタリア アリア集 2
のいずれす・えすぴー・あーかいゔず でんせつ・の・うたごえ・3 いたりあ ありあしゅう・2
Legendary Voices from the Past 3 -Italian Arias 2-
(VARIOUS)
収録曲
|
1 |
まことの指輪を(02'54") まこと・の・ゆびわ・を Prendi I'anel ti dono 「夢遊病の女」より |
||
|---|---|---|---|
| 作詞:ROMANI FELICE / 作曲:Bellini, Vincenzo Tagliavini, Ferruccio | |||
|
2 |
なつかしい眺め(02'59") なつかしいながめ Vi ravviso(Sonnambula) 「夢遊病の女」より |
||
| 作詞:ROMANI FELICE / 作曲:Bellini, Vincenzo Shalyapin, Fyodor Ivanovich | |||
|
3 |
盲目の女の唄(03'47") もうもく・の・おんな・の・うた Voce di donna 「ジョコンダ」より |
||
| 作詞:Arrigo Boito / 作曲:Ponchielli, Amilcare Onegin, Sigrid | |||
|
4 |
おおローラ(シチリアーナ)(02'37") おお・ろーら(しちりあーな) Lola(Siciliana) 「カヴァッレリーア・ルスティカーナ」より |
||
| 作詞:TARGIONI TOZZETTI GIOVANNI、MENASCI GUIDO / 作曲:Mascagni, Pietro Melton, James | |||
|
5 |
シチリアーナ(02'17") しちりあーな Cavalleria Rusticana-Siciliana(Thy Lips Like Crimson Berries) 「カヴァッレリーア・ルスティカーナ」より |
||
| 作詞:TARGIONI TOZZETTI GIOVANNI、MENASCI GUIDO / 作曲:Mascagni, Pietro Martinelli, Giovanni | |||
|
6 |
衣装をつけろ(03'52") いしょう・を・つけろ Vesti la glubba 「道化師」より |
||
| 作詞:LEONCAVALLO RUGGERO / 作曲:Leoncavallo, Ruggiero Martinelli, Giovanni | |||
|
7 |
おおコロンビーナ(02'13") おお・ころんびーな O Colombina(Serenata) 「道化師」より |
||
| 作詞:LEONCAVALLO RUGGERO / 作曲:Leoncavallo, Ruggiero Melton, James | |||
|
8 |
もう道化師じゃない(04'12") もう・どうけし・じゃない No, Paliaccio, non son! 「道化師」より |
||
| 作詞:LEONCAVALLO RUGGERO / 作曲:Leoncavallo, Ruggiero Martinelli, G.(ten)&Chorus of "Metropolitan Opera" | |||
|
9 |
この柔らかなレースの中で(02'38") この・やわらかな・れーす・の・なか・で In Quelle Trine Morbide 「マノン・レスコー」より |
||
| 作詞:LEONCAVALLO RUGGIERO、PRAGA MARCO、OLIVA DOMENICO、GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Tebaldi, Renata | |||
|
10 |
ロドルフォの物語(04'16") ろどるふぉ・の・ものがたり Racconto di Rodolfo 「ボエーム」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Martinelli, Giovanni | |||
|
11 |
私の名はミミ(04'21") わたし・の・な・は・みみ Man nennt mich Mimi 「ボエーム」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Dux, Claire | |||
|
12 |
私の名はミミ(04'35") わたし・の・な・は・みみ Mi Chiamano Mimi 「ボエーム」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Olivero, Magda | |||
|
13 |
妙なる調和(03'10") みょうなる・ちょうわ Recondite armonie 「トスカ」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Tagliavini, Ferruccio | |||
|
14 |
歌に生き、恋に生き(03'06") うた・に・いき、こい・に・いき Vissi d'arte, vissi d'amore 「トスカ」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Olivero, Magda | |||
|
15 |
歌に生き、恋に生き(03'12") うた・に・いき、こい・に・いき D'Art et d'Amour 「トスカ」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Vallin, Ninon | |||
|
16 |
歌に生き、恋に生き(03'20") うた・に・いき、こい・に・いき Vissi d'arte, vissi d'amore 「トスカ」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Tebaldi, Renata | |||
|
17 |
星は光りぬ(03'30") ほし・は・ひかりぬ E lucevan le Stelle 「トスカ」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Tagliavini, Ferruccio | |||
|
18 |
ある晴れた日に(04'43") ある・はれた・ひ・に Un bel di vedremo 「蝶々夫人」より |
||
| 作詞:GIACOSA GIUSEPPE、ILLICA LUIGI / 作曲:Puccini, Giacomo Tebaldi, Renata | |||
|
19 |
フェデリーコの嘆き(04'13") ふぇでりーこ・の・なげき E la solita storia 「アルルの女」より |
||
| 作詞:MARENCO LEOPOLDO / 作曲:Cilea, Francesco Crooks, Richard | |||
|
20 |
フェデリーコの嘆き(03'49") ふぇでりーこ・の・なげき Lamento di Federico 「アルルの女」より |
||
| 作詞:MARENCO LEOPOLDO / 作曲:Cilea, Francesco Bjorling, Jussi | |||
time:0.35 s・

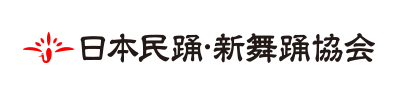
作品紹介
最新のデジタル技術によって貴重なSP音源の針音ノイズを除去して甦らせる〈ノイズレスSPアーカイヴズ〉シリーズ。19世紀末から20世紀前半に活躍した伝説的な歌手達の名唱を集めて贈るクラシック音楽・歌曲編。第二回発売は、イタリア関連の作品集。(2010年ノイズレス・ヴァージョン)
解説:山角浩之
「現代に甦る奇跡の記録」
財団法人 日本伝統文化振興財団理事長 藤本 草
録音機の歴史は、エジソンの円筒式録音機以来、円盤型のSP盤、オープンリール、カセット、DAT、MD、そしてハードディスク、メモリーレコーダーヘと現在まで飛躍的に進化して参りました。その中でもSP盤は、1950年代までの50年以上にわたり、録音記録の大きな役割を果たしています。日本のレコード会社によるSP盤の発売は明治末期から始まり、膨大に記録された名演奏は、現在までSP盤オリジナル音源として数多く残されています。
その当時の日本の伝統音楽界は、多くのジャンルに優れた演奏家が群雄割拠するまさに黄金時代であり、また文明開化以来の洋楽受容期を経た西洋音楽、流行歌にも盛んな演奏活動が大きく花開いた時代であり、現代のCDにも相当する最新メディアであったSP盤はその大きな推進役でした。
このようにして現代に残された貴重なSP盤ですが、SP盤の溝をレコード針が通るために発生するスクラッチノイズ、何らかの原因で混入した磁気ヒズミ、物理的なキズ、当時のマイクロフォン性能に起因する音量不足、不安定な回転ムラなど、残念ながら多種多様なノイズが含まれており、ノイズを感じない状況で演奏を味わって聴くことは不可能と思われておりました。
SP盤から聴こえる音楽に熱狂した当時のリスナーに思いを馳せ、これらの歴史的録音記録を現代に甦らせたいと考えた私ども財団は、SP盤音源のノイズリダクション製作に画期的な手法で取り組んでおられる内藤孝敏氏に依頼し、その最新の音源修復技術によって大きな音質改善を得た「ノイズレスSP盤」をシリーズ制作・発表することとなりました。
半世紀を超えて現代に甦ったオリジナル録音の魅力をCD盤に収録し皆様にお聴き頂ける。これはまさに、「現代に甦る奇跡の記録」と言えるのではないでしょうか。